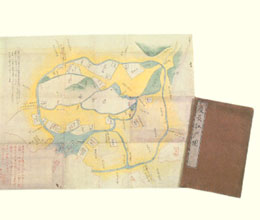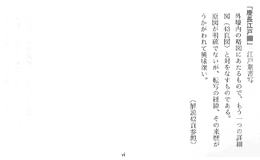| (14) 地誌
ある地域の自然・社会・文化などの地理的な事項を記述した書物を、一般に地誌という。 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 『和泉名所図会』『江戸名勝志』『河内名所図会』『京都順覧記』『山州名跡志』 『世界国尽』『摂観余光』『摂津名所図会』『但馬考』『摂州多田温泉記」『東海道駅路鈴』「東海道名所図会』『諸国奇談東遊記』『浪華の賑ひ』『日本名山図絵』『播磨国細見図』『坂東・西国・秩父観世音霊場記』『兵庫名所記」『本朝奇跡談』『都名所車』『都名所図会』『大和名勝志』『大和名所図会』(五 |
||||