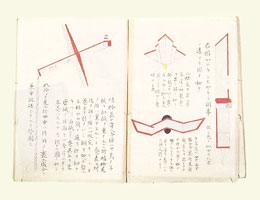| かった。中絶した『偐紫田舎源氏』の流れを汲むものが登場するのである。その中でも有名なものは、『釈迦八相倭文庫』(応賀作、国貞画、安政六年刊)と『其由縁鄙俤』である。藩医であった草鹿家同様、幕末の医師坪井信良の手紙にも、医師佐渡家の女性(実母)ヘのお年玉として、先の二書を購入している記事がある(『幕末維新風雲通信』安政二年一月二十一日付書翰)。そして、『偐紫田舎源氏』も佐渡家の実母に送っている。この本の出版禁止後の面白い記事でもあり、手紙の一部を引用しておく(安政元年二月十六日付書翰)。
先年公世之処、板本御取立ニテ滅板ニ成申候者ニテ、世上ニ至テ少キ処ニテ、諸
人渇 仰之処也。然ルニ付テ、一奸生当年竊ニ上木仕候也。尤も盗板故、版も出来
も見苦敷 御坐候得共、是ニテ鄙ノ俤初篇と之連続ニ相成申候也。
『偐紫田舎源氏』は絶版になったが、その人気は海賊版を生むことになった。それを入手して送ったのである。その結果、『共由縁鄙俤」初編の話へと通じるというのである。
もちろん、『釈迦八相倭文庫』も『其由縁鄙俤』も当文庫にある。このことは、幕末期の合巻読者として、共に医師である草鹿家、佐渡家の女性達といった具体的な享受者像が明らかになる興味深い資料でもある。
(小谷) |