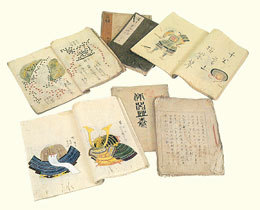| 其後天保二年マデ江戸表へ御参勤毎御供被仰付。文政二年正月御加増拾石下賜。 八年 正月御加増拾右下賜、都合百七拾石拝領仕。天保二年三月梅芳院様御病中出 精相勤候 付、御熨斗目井御目録拝領仕。六年江戸御供被仰付。八年三月御近習・ 御医師御免仰 付ラレ、十一年四月医学頭仰付ラレ、十四年医学方骨折候付御羽織 拝領仕。嘉永三年 十月利義公近習御医師被仰付。同年十一月栄操院様就御病気、 金沢表へ早打御使仰付 ラレ罷越候処、従斉泰公目録頂載仕。四年江戸御供被仰付 。安政二年利義公於江戸表 就御大病、御人指ニテ早打御使被仰付。慶應元年正月 及老年候ニ付隠居被仰付、年々 銀拾枚下賜是迄ノ通医学世話可仕旨被仰渡。且又 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
数年相勤候付、御目録銀子二枚頂戴 仕罷在候処、明治二年九月七十八才ニテ病死 一、八代 草鹿甲子太郎 |
||||